
新しい家族の仲間になる猫との暮らしは楽しみに満ちていますが、健康的な生活のためには正しい飼い方と栄養管理が重要です。この記事では初めて猫を飼う方に向け、猫の餌選びのポイントをお伝えします。
猫の餌選びにおいては、年齢や体重を考慮した栄養バランスが鍵。市場には子猫用、成猫用、シニア用など豊富なフードが取り揃えられています。
また、缶詰とドライフードを組み合わせるなど、食事のバリエーションを増やすことで愛猫が食事に飽きてしまうのを回避するのもポイントです。
こちらの記事を最後まで読んでいただければ、猫の餌の正しい選び方はもちろん、猫が餌を食べてくれない場合の対処法なども知ることができます。
5分ほどで読める内容にまとめていますので、さっそく読んでみてください!
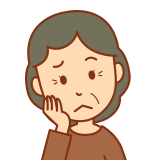
猫用の餌を切らしてしまったんですけど、人間の食べ物をあげてもいいでしょうか?
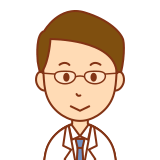
なるべくなら猫用のフードで統一するのが理想的です。人間の食べ物は猫にとって塩分量などが多かったり、有害なものもあるので、むやみに与えるのはやめましょう!
猫の餌を選ぶポイント
猫の餌選びは、健康維持に直結する重要な要素です。短期間で適した餌を見つけることは困難ですが、以下の情報を参考にしていただき、理想的なフードを見つけてみてください。
また、多頭飼育を検討されている場合は、複数種の餌を用意することも視野に入れておきましょう。
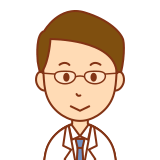
猫にとってご飯の時間は数少ない楽しみの1つです。コスト削減のために安いものを選びたくなる気持ちはわかりますが、できる限り猫にとって理想的なフードを用意してあげてくださいね♪
【ポイント①】年齢から餌を考える
猫の餌を見てみると、ほとんどのメーカーで年齢別にフードが販売されていることがわかります。人間にも離乳食や介護職があるように、年齢に応じた食事が必要です。
猫の年齢に応じた餌選びは、健康維持に欠かせない重要なステップでもあります。成長段階に合わせた栄養補給をすることで、猫の長期的な健康を支えます。
例えば子猫期は成長が著しく、たんぱく質やビタミンが必要です。成猫期になると維持段階となり、バランスの取れた栄養が求められます。シニア期では関節や内臓など、個別の部位をフードでサポートします。
まずはご自身の愛猫の年齢を確認し、適切なフードの種類を考えてみましょう。
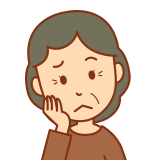
猫の餌として販売されているからって、どんな餌でもOKってことではないんですね。
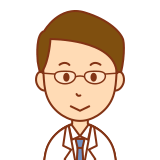
年齢以外にも「去勢・避妊後用」「室内外向け」「穀物不使用」など、メーカーによって細かく用途を分類してくれているパターンもありますよ♪
【ポイント②】餌の種類から考える
猫の餌には大きく分けて「ウェットフード」「ドライフード」「セミモイストフード」の3種類があります。ウェットフードはシーチキンのようにドロっとした特徴があり、ドライフードは水分が少ない代わりに栄養素が凝縮されています。
セミモイストフードはちょうど中間のような位置にあり、ドライフードよりも粒がやわわかいため、高齢犬でも食べやすいのが特徴です。
これらは主に水分と栄養素の含有量に違いがあり、ウェットフードに近いほど水分量が多く、ドライフードに近いほど栄養素が豊富となっています。
基本的には肉源が主成分で、添加物が最小限に抑えられている高品質なフードが理想的です。ですので無添加やグレインフリーのフードも選択肢として有力と言えるでしょう。
ただし猫によっては好き嫌いがハッキリしているため、どれか1つだけを食べさせるのではなく、様子を見ながら一通り試してみるのも効果的です。
また複数の餌を組み合わせることで空腹の機会を減らしつつ、水分や栄養素を理想的に摂取してもらうことができます。
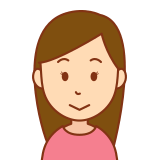
我が家の猫はウェットフードに目がないんですよね!でも、それだけだと栄養がカバーできないから、基本的にはドライフードがメインになっています☆
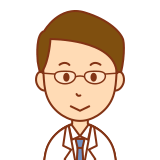
ウェットフードは個包装になっているので、1食あたりの食事量を調整できないのはデメリットです。その点、ドライフードは保存管理がしやすいので、猫によって分量も調整しやすいですし、飼い主としても助けられているかたは多いでしょう♪
【ポイント③】餌の味から考える
餌の味は猫の食欲と満足度に直結します。猫は繊細な味覚を持っており、好みは個体によって大きく差が出ます。肉系や魚系、野菜を主成分とした様々なフレーバーが市場に揃っていますが、愛猫が特に好む味を見つけることが重要です。
猫が好む味や香りを把握するために、いくつかの異なるフードを試すことがおすすめです。ただし頻繁に新しい餌に変更するのは、猫にとってストレスになってしまう可能性もあります。
そのため猫の食いつきが悪くなったり、飽きる素振りを見せるまでは同じ餌を与え続け、飽きたと感じたタイミングから新しい餌を少しずつ混ぜていくのが理想的です。
唐突に新しい餌に変更してしまうと消化不良を起こしてしまう可能性があるので、既存の餌に少量を混ぜつつ1〜2週間ほど期間をかけて移行しましょう。
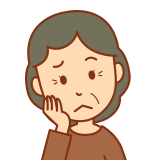
人間にも味の好みはあるし、同じものばっかりだと飽きちゃいますもんね。
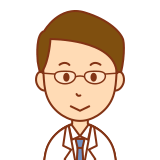
もし餌を変更する場合は、現在のフードに対して新しいものを10%含めて与えてみてください。問題なく食べているようであれば2日目は20%、3日目は30%と徐々に分量を変えていきましょう☆
【ポイント④】餌の栄養面から考える
猫の健康維持において、餌の栄養面は極めて重要です。まず、肉源が主成分であることが理想的です。猫は肉食動物であり、たんぱく質が必須の栄養素となります。
良質なたんぱく質は筋肉の維持や免疫力の向上に寄与します。また、脂質やビタミン、ミネラルもバランスよく摂取することが重要です。商品の裏面などに記載されている原材料リストを確認し、添加物が最小限に抑えられた高品質なフードを選ぶことが健康につながります。
現代では無添加やグレインフリーのフードも注目されており、これらの選択も検討する価値があります。特に、猫の健康状態や年齢に応じて、必要な栄養素のバランスを考慮して餌を選ぶことが重要です。
獣医師のアドバイスも積極的に取り入れ、猫が必要な栄養素をバランスよく摂取できるよう心がけましょう。総合的な栄養管理は、猫の元気な毎日を支え、健康寿命を延ばす鍵となります。
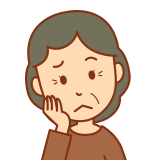
猫は穀物が消化できないって聞いたんですけど、穀物が使われている餌は与えないほうが良いのでしょうか?
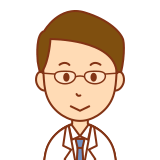
たしかに猫は穀物を消化することができません。ですがそれは穀物を生で食べた場合のケースで、加熱調理をした穀物であれば猫でも負担なく消化することができます。どうしても不安と感じるのであれば、グレインフリー(穀物不使用)の餌を用意するのも1つの方法ですよ☆
猫が餌を食べない理由
『せっかく時間をかけて餌を選んだのに、食べてくれない。』『昨日までは普通に食べていたのに、今朝から食べなくなってしまった。』猫を飼っていると、こういった経験をされることもあるでしょう。
ここでは猫が餌を食べなくなってしまう理由について、解説いたします。
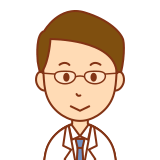
意外と単純な理由で食べるのをやめてしまう猫もいるので、まずは冷静に1つずつ原因を考えてみましょう☆
【理由①】味に飽きた・美味しくない
猫が餌を食べない理由として、猫が「味に飽きた」ことが挙げられます。猫も私たちと同様に、同じ味の餌を長く食べると飽きてしまうことがあります。食事のバリエーションを増やすために、定期的に異なる味やフレーバーの餌を試してみると、猫が食事に興味を持ちやすくなるので効果的です。
また、もう一つの理由は「餌が美味しくない」と感じている可能性です。猫は繊細な味覚を持っており、餌の質や味に敏感です。食事の際に餌が美味しくないと感じると、食欲が低下してしまうことがあります。
長期的な保存に向いているドライフードでも、一度開封したまま放置していると、比較的短期間で味や香りが変化してしまいます。特に保存期限が過ぎているものの使用は避け、なるべく新しい餌を提供するようにしましょう。
飼い主は愛猫の好みに合わせた餌の選定が大切です。時折異なるフレーバーや形状の餌を提供し、美味しさを感じられる食事環境を整えましょう。これにより、猫の食欲が向上し、元気な毎日を過ごすことができます。
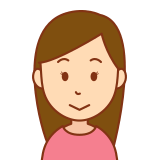
人間の食べ物も湿気で味や食感が変わることってありますもんね!
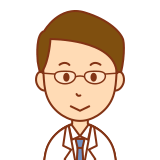
猫は環境の変化があまり得意ではありません。特にネガティブな変化には敏感なので、明らかに嫌がる素振りを見せた場合は、新しい餌を用意してあげましょう☆
【理由②】満腹で食べられない
猫が餌を食べない理由の一つとして、「満腹」が考えられます。猫は自分の食欲をコントロールし、満腹感を感じた場合は食事を拒否することも珍しくありません。これは、飼い主が与えた量が適切であるかどうかを考えさせられるポイントです。
放し飼いの猫であれば、すでに他のエリアで餌を得ていたり、室内猫であればおやつを食べたりしている場合などが考えられます。そういったケースでは、本来の食事に対する欲求が薄れ、満腹感を覚えてしまいます。
適切な栄養素を摂取してもらうためにも、可能な限り食事の時間帯や回数は人間がコントロールして、余分なエネルギー摂取を抑えることが重要です。食事量が多い場合は1食あたりの給餌量を調整してみるのも良いでしょう。
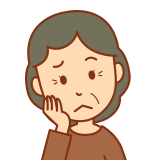
満腹なら食べられないのもしかたないですよね…。
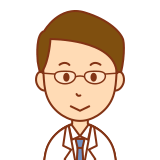
猫がよく食べるからといって、適正量を大幅に超える餌を与える飼い主のかたもおられますが、肥満や生活習慣病の原因になってしまうので注意してくださいね!
【理由③】環境が落ち着かない
猫が餌を食べない理由の一つには、「環境が落ち着かない」ことも挙げられます。猫は繊細な動物で、周囲の環境変化やストレスが食欲に影響を与えること多いです。例えば、新しい家庭環境や新しいペット仲間が加わった場合、猫は緊張や不安を感じ、その影響で食欲が低下することがあります。
飼い主は猫の食事環境を整え、リラックスできる場所を提供することが重要です。安全な場所に食器を配置し、他のペットや外部の騒音から遠ざけることで、猫が食事をする際に安心感を得ることができます。
また大きな環境の変化だけでなく、食器が新しいものに変わるなどの小さな変化にも反応してしまう猫がいます。新しい餌に興味が持てないといったケースも報告されているので、一度過去に使っていた食器や、以前食べていたフードに戻してみて様子を見てみましょう。
猫が餌を食べない時には、環境の変化を考慮し、優しさと理解をもって接することが大切です。猫が心地よく食事をとることができるような環境づくりが、ペットとの円満な生活に繋がります。
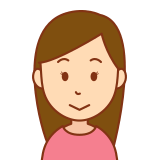
人間的には大したことなくても、猫からすると大きな変化になることがあるんですね!
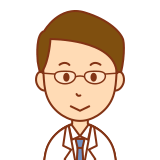
神経気質な猫は、些細なことで食事を摂らなくなってしまいます。特に飼い始めて半年未満の場合は、建物そのものに慣れていない可能性があるので、優しく見守ってあげましょう!
【理由④】病気で食欲がわかない
猫が餌を食べない理由の1つが「病気」です。猫は食欲が低下することで、体調不良や病気のサインを示すことがあります。例えば、歯のトラブルや消化器官の問題、内臓疾患などが原因で、猫は食べることが辛くなります。
猫が通常よりも食欲が低い場合や、急激に食事量が減った場合には注意が必要です。具体的な症状として、嘔吐・下痢・体重減少などが挙げられます。これらの症状が見られた場合は、速やかに獣医師の診察を受けることが大切です。
病気の場合、早期の発見と治療が重要です。獣医師が猫の健康状態を診断し、適切な治療法を提案してくれます。また、病気の予防として、定期的な健康診断と予防接種もお忘れなく。
飼い主の愛情と注意が、猫の健康を守る大切なカギです。病気が疑われる場合は、専門の獣医師に相談し、猫の元気な生活をサポートしましょう。
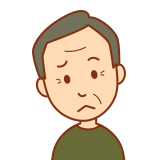
猫は病気であることを申告できないから、人間がサポートしてあげなくてはいけませんね。
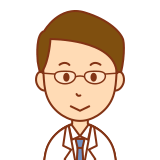
普段から猫の状態をチェックしておき、健康時との違いにすぐ気付けるようにしておきましょう☆
【理由⑤】加齢でご飯の量を食べられない
猫は「加齢」で餌を食べなくなることもあります。猫も人間同様に年をとると、食欲や消化力が低下し、食事に対する関心が薄れるためです。このような変化は自然なものですので、飼い主が理解と配慮をしてあげましょう。
加齢による餌嫌いの場合、柔らかくて嗜好性の高いフードを提供することが大切です。歯の健康維持のためにも、噛みごたえが適度なものを選ぶと良いでしょう。また、食事の回数を増やして少量ずつ与えることで、胃腸への負担を減らすことができます。
特に7歳以上になると中高年期に差し掛かります。早い場合にはこのあたりから年齢による食欲の低下が見られたり、フードの好みにも変化がでてくるので、状況に応じて餌の種類を変化させてみてください。
加齢期の猫には、特に優しい愛情と手入れが必要です。定期的な健康診断や、獣医師のアドバイスを受けることで、適切な栄養と食習慣をサポートできます。食事の時間を楽しみながら、年齢に合ったケアを提供することで、猫との絆を深めましょう。
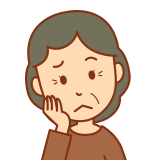
猫で7歳って、人間でいうと何歳くらいに相当するんでしょうか?
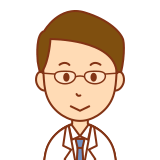
猫の7歳は人間の44歳に相当します。11歳になると還暦に相当するので、フードの切り替えをする時期としては、おおよそ7歳から〜11歳に多く見られますね。
猫が餌を食べない時の対処法
『餌に飽きているような感じがある。』『病院に連れて行ったけど、異常は見つからなかった。』といったケースは、多くの飼い主が経験されているはず。
特に子猫や成猫になったばかりの個体は、食事が安定しないことも珍しくありません。そこで猫が餌を食べない時の対処法をご紹介いたします。
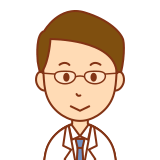
体調に問題がなければ、こちらの内容を一通り試していただくことで、餌への食いつきはアップしているはずです!今後役立つ情報にもなりますので、ぜひ覚えていってくださいね♪
【対処法①】運動をさせ消化を促してみる
まずは「運動」をさせて消化を促してみましょう。運動は猫の体調を整え、食欲を刺激する効果があります。特に、猫は狩猟本能を持っているため、運動を通じてこの本能を刺激することで食欲が向上します。
飼い主は、猫の好みに合わせたおもちゃや遊び道具を使ってアクティブに遊ぶことを意識してください。羽根付きのおもちゃやネズミ型のぬいぐるみなど、猫が興味を引くアイテムを用意してあげましょう。遊びを通じて猫の体を動かし、エネルギーを消費させることで、食欲が戻る可能性が高まります。
ただし食後すぐの運動は吐き戻しを誘発してしまうので注意が必要です。流れとしては食事前に遊びを取り入れるのが理想的です。
また、運動はストレス解消にもつながります。環境の変化や新しい仲間が加わった場合、猫はストレスを感じることがあり、それが食欲不振につながることは珍しくありません。適度な運動を提供することで、猫のリラックス効果が期待できます。
ぜひ猫と一緒に楽しい運動を通じてコミュニケーションを深め、健康的な生活をサポートしましょう。
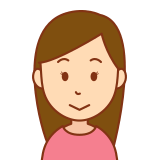
たしかに動けばお腹は空きますよね!
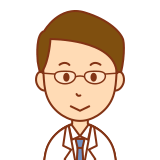
猫の性格にもよりますが、普段からあまり動かないタイプの猫は、運動をさせてあげることで食欲が回復することが多いです☆
【対処法②】フードの種類を変えてみる
猫が餌を食べない時は「餌の種類を変えてみること」もポイントです。猫も私たち人間と同じように、食事に対して好みがあります。同じ味や形状の餌を続けて与えると、猫も時に飽きてしまいます。
例えば、ドライフードから缶詰などのウェットフードに変えることで、猫は新しい刺激を受け、食欲が戻ることがあります。ただし急激な変化は猫を驚かせてしまうことがあるため、新しいものを取り入れる際は、現在のフードに混ぜながら徐々に変えていくと良いでしょう。
飼い主は猫の好みにも気を配り、食べることを楽しい体験に変えてあげる工夫が大切です。美味しそうな香りや新しいフードの登場に興味津々な猫は、食欲を刺激されやすくなります。
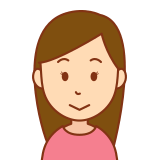
人気のカレーライスだって、何日も続くと飽きてしまいますもんね。猫もたまには新しいものを食べて気分転換が必要なんですね!
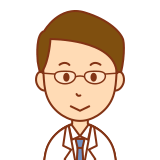
我が家の猫ちゃんたちは、ドライフードだけに限定せず、毎日ウェットフードも併用して変化を与えています。そのようにしてからは、餌を残してしまうことがなくなりました☆
【対処法③】ふりかけなどで味を変えてみる
餌の種類を変えるのが難しい場合は、「味を変えてみること」も効果的です。猫も私たちと同じく、同じ味に飽きてしまうことがあります。そのため、新しい味を試してみることで、猫の興味を引き出すことができます。
例えば猫用に作られた“ふりかけ”を用いて、魚味から鶏味に変えるだけでも、猫にとっては大きな変化となり食欲アップが期待できます。ふりかけが用意できない場合は、“ちゅ〜る”を少し混ぜてあげるだけでも十分な効果が得られます。
ほかにもおやつ用の鰹節をすり潰して、フードに混ぜ合わせてみるなど、少しの工夫で改善されることもあるので是非お試しください。
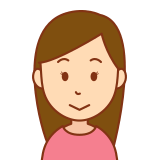
ちゅ〜るが嫌いな猫って見たことがないし、それならしっかりとご飯を食べてくれそうですね♪
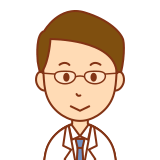
一時的にしか効果がないかもしれませんが、新しい餌へ変更していく仮定では十分に役立つ手法なので、ぜひ覚えておいてくださいね☆
【対処法④】どうしても食べない場合は病院へ
どのような方法を用いても猫が食事を摂らない場合は、「病院へ連れていくこと」が最優先です。猫は食欲が低下すると体調が優れなくなることがあり、これは様々な病気や健康問題のサインとなります。
病気や不調が原因で食欲がなくなる場合、早期の診断と治療が重要です。獣医師は専門知識を持ち、猫の健康状態を正確に判断できます。具体的な症状や行動の変化を獣医師に伝えることで、的確な診療も受けやすくなるでしょう。
また時間帯や地域がらの問題で、即座に動物病院へ連れて行くことが困難な場合は、水分補給だけでも促してみてください。
寒い時期であれば体が冷えないように温めの水にしてみたり、スープ系のフードであれば口にしてくれるケースがあります。また人気のおやつである“ちゅ〜る”には、水分補給に優れたタイプも販売されているので、そういったものを用意しておくのも良いでしょう。
猫が元気を取り戻し、健康に過ごすためには、飼い主の早めの行動が必要不可欠です。病院での専門的な診察とアドバイスを受けることで、猫の健康被害の拡大を留めることに繋がります。
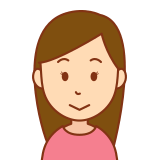
動物病院へいくことを優先しつつ、水分補給を試してみるのが良いってことですね!
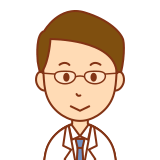
ご飯を食べることは水分補給にも繋がります。ですので餌を口にしていなければ、水分が不足している可能性が高いです。そのため、まずは胃に負担がかからないように水分補給をさせてあげてください。
【まとめ】猫の餌選びは人間の重要な役割
今回は猫の餌を選ぶポイントや、餌を食べなくなった時の対処法について解説をまとめました。猫の餌には豊富な種類が用意されており、状況に応じて与える内容を変化させる必要があります。
特に多くの猫は食べることを数少ない楽しみに感じているので、飼い主としても最善をつくし、快適な食事の時間を送れるようにサポートしてあげましょう。
また、猫にとって至福のひとときである食事も、環境や状態によっては受け付けない場合があります。給餌量を管理することはもちろん、年齢や空腹度合いを考慮して、ベストな餌やりを目指しましょう。
はじめは試行錯誤が必要ですが、猫と時間をともにしていれば、趣味嗜好がわかるようになってくるはずです。特に好きなフードがあれば、明らかに反応が変わる猫は多いので、観察しながら調節してみてください。
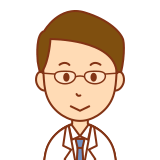
猫の習性上、一度のご飯を数回に分けて食べるケースもあります。特に迎え入れてから、人馴れするまでは分割することがあるので、しばらくは離れて様子を見てあげるのも大切です☆
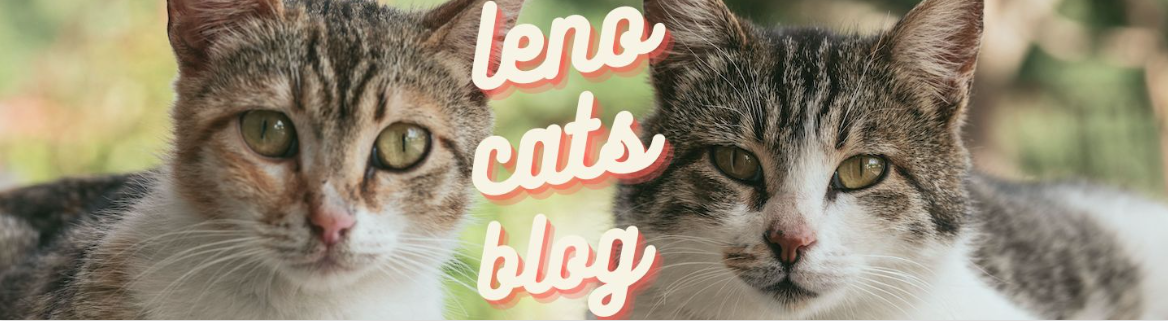






コメント